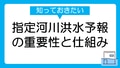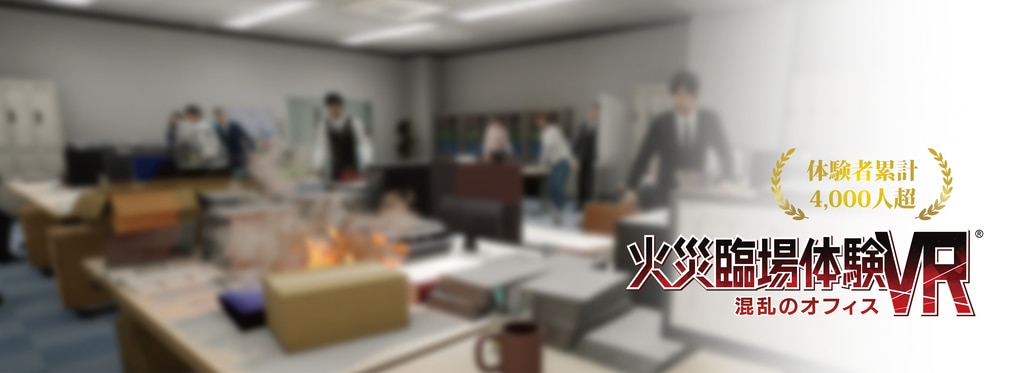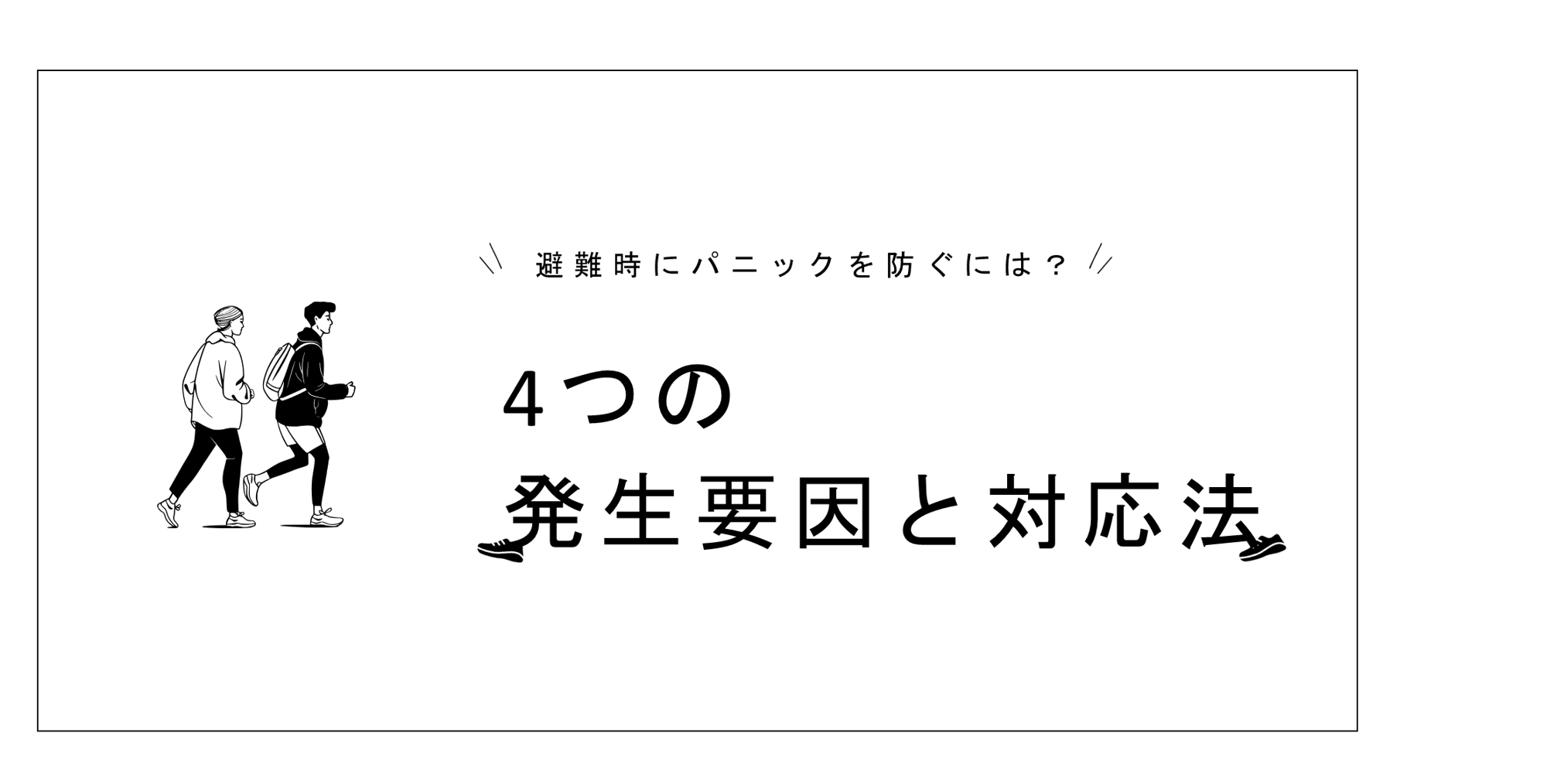
避難時にパニックを防ぐには?4つの発生要因と対応法
災害は、ある日突然やってきます。
「いざという時、自分はちゃんと動けるだろうか…?」
そう不安に感じたことはありませんか?
実は、多くの人が避難行動をとる中でパニック状態になるのは、特別な人だけではありません。誰もが一定の条件下で冷静さを失いかけるのです。
でも大丈夫。
「なぜ人はパニックになるのか」をあらかじめ知っておけば、怖さをコントロールし、落ち着いて行動する力が自然と備わっていきます。
本記事では、避難時にパニックが起きやすくなる4つの心理的条件と、それを防ぐための具体的な備えについて紹介します。
目次[非表示]
要因その① :差し迫った危険を感じたとき(思い込みが恐怖を加速させる)
「このままでは命が危ない!」と感じた瞬間、人はとっさに逃げようとします。
それが本当の危険でなくても、「崩れるかも」「火が迫ってるかも」といった思い込みが恐怖を増幅し、周囲を巻き込んだパニックにつながることがあります。
●どう備える?
- 日頃から避難訓練に参加し、事実と感情を分けて判断する習慣を持ちましょう。
- 家族や同僚と避難の流れをシミュレーションしておくと、体が自然に動くようになります。
- 防災マップや非常口の位置を「見ておく」ことも安心材料になります。
要因その②:脱出の可能性があるとき(チャンスが見えた瞬間の混乱)
「こっちからなら逃げられるかも!」と感じた瞬間、人は我先にと出口に殺到します。
結果として通路が詰まり、通行不能や転倒といった新たな危険が生まれ、パニックが起きてしまいます。
●どう備える?
- 建物や地域で複数の避難ルートを事前に確認しておく。
- 「正面玄関だけが出口ではない」ことを体験しておく訓練が有効。
- 家族や周囲と「分散避難を心がける」ルールを決めておくと安心です。
要因その③:脱出口に制約があると感じたとき(閉塞感が恐怖を呼ぶ)
「この出口じゃ間に合わない」「混雑してて抜けられない」
そう感じると、人は極度の不安に陥り、冷静な判断が難しくなります。
●どう備える?
- 非常口や非常階段、脱出用具の場所を日頃から確認しておく。
- 家では「2方向から避難できるか」を意識して家具の配置や避難経路を検討する。
- 防災グッズと一緒に避難ルートの図を掲示しておくのも効果的です。
要因その④:情報が届かない・誤っているとき(不安の連鎖が始まる)
災害時は通信手段が制限され、正しい情報が入手できないことがあります。
その結果、デマや誤報に流されて誤った行動をとり、パニックが連鎖的に広がることがあります
●どう備える?
- 家族や地域で連絡方法や集合場所を事前に共有しておく。
- 無線機や防災ラジオ、防災アプリなど複数の情報源を準備する。
- 非常時はSNSよりも、公的機関の情報を優先して確認しましょう。
パニック時に自分を落ち着かせる方法
どんなに備えていても、実際に恐怖を感じることはあります。そんな時は:
- 深呼吸(3秒吸って6秒吐くを数回)
- 自分の五感に集中(今、足は?何が聞こえる?)
- 一人で判断せず、周囲と連携する

また、日常的に不安を感じやすい人は、カウンセリングなどのサポートも検討しましょう。
おわりに:不安は「備え」で小さくなる。そして、行動が共助をつくる
パニックになるのは、心が弱いからではありません。
人は、正体のわからないものに不安を抱くのです。
でも、「どんな時にパニックが起きやすいか」「それにどう備えるか」を知っていれば、
あなたや大切な人の命を守る力になります。
「備えていたから、冷静でいられた」
そんな自信が、安心を支えてくれるはずです。
N-HOPSで「行動できる力」を持ち歩こう
とはいえ、日々の忙しさのなかで繰り返し訓練するのは難しいものです。
地域の役割を担いたくても、経験や知識に自信が持てない人も多いでしょう。
N-HOPSは、そんな不安を“行動できる力”に変える防災アプリです。
- 訓練していなくても、「何をすればいいか」がわかる
- 特別な知識がなくても、地域を支える行動ができる
- 誰かに頼らず、自分の行動で共助に加われる
N-HOPSは、経験に依存しない“新しい共助”を可能にします。
経験がなくても、「ふるまい」は持ち歩ける。
あなたも、共助の一員になれます。