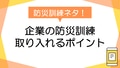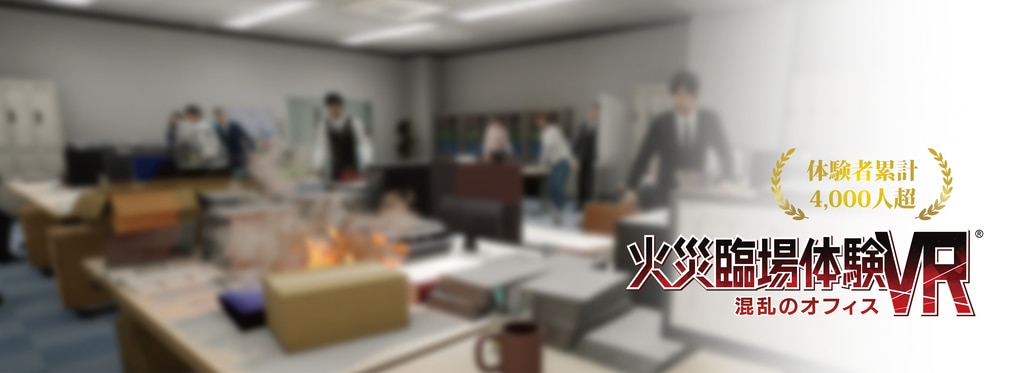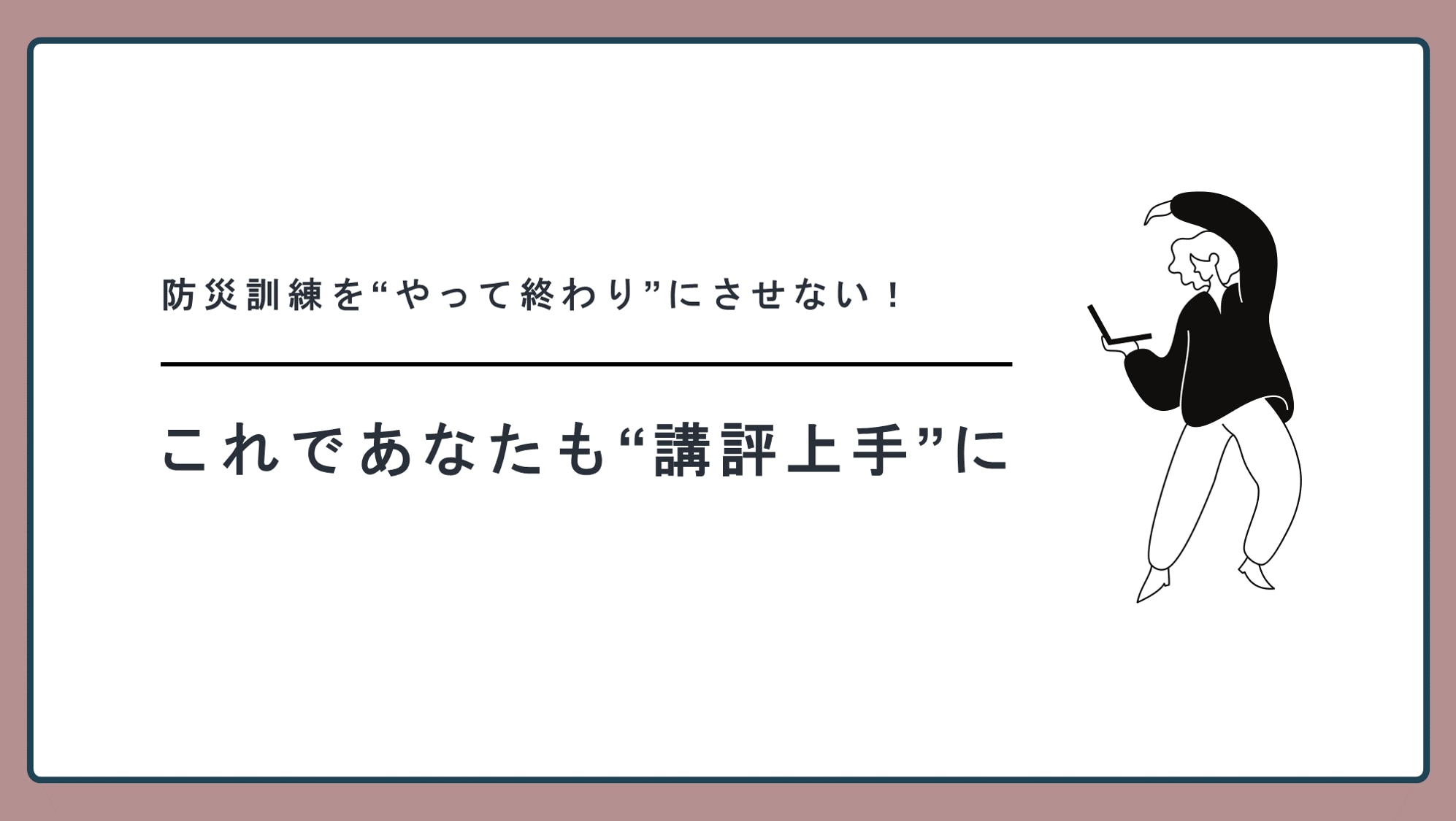
防災訓練を“やって終わり”にさせない!これであなたも“講評上手”に
ある日の夕食どき。
ふとした会話の中に、防災訓練の大切なヒントが隠れていました。
「今日ね、避難訓練やったよ」
そう話したのは、わが家の中学生になる子ども。
聞いてみると、校内放送が流れ、先生の指示で整列し、グラウンドへ移動する——そんな流れの訓練だったそうです。
「気づいたことあった?」と聞くと、
「うーん・・・特にないかな」との返答。
この何気ない一言が、少しだけ心に残りました。訓練って、ただ“やる”だけでいいんだっけ?そんな問いが、ふと浮かんだのです。
目次[非表示]
企業の防災訓練、よくある5つのパターン
学校の訓練では「静かに整列して避難すること」が重視されますが、企業においては、より実務的な判断力や連携力が求められます。以下のような訓練パターンがよく見られます。
避難誘導型:
- 建物内から指定の避難場所まで、全員を安全に誘導する訓練です。
- 経路の確認や声かけの仕方など、初動対応の確認が目的です。
機器実践型:
- 実際に消火器や消火栓を使いながら、初期の火災対応などの体験を行います。
- 消火器などの使い慣れていない機器に慣れてもらうのに有効です。
安否確認型:
- 在宅勤務中の社員や離れた拠点の社員を対象に、安否確認メールやツールを用いた対応訓練を行います。
- BCP(事業継続計画)対策の一環です。
通報・連絡型:
- 災害時の情報収集や社内連絡体制の確認を行います。
- 正確な情報を誰が、どの手段で、どこに伝えるかを明確にする訓練です。
シナリオ対処型:
- 混乱や被害のある状況をあえて設定し、参加者がその場で判断・対応を求められる実践型の訓練です。
- 状況の変化に柔軟に対応できる力を養うのが目的です。

訓練は“やった後”が本番。講評で行動が変わる
防災訓練で最も大切なのは、「やったかどうか」よりも「やってどうだったか」をきちんと振り返ることです。つまり、読者である皆さんが行う講評が、その日に行った訓練の価値を決めると言っても過言ではありません。
講評で大切にしたいのは、次の3つの視点です。
- 事実の共有
何が起きたのか、誰がどんな行動をとったのかを、できるだけ具体的に確認します。 - 気づきの引き出し
その行動を選んだ理由や、迷ったこと、困ったことがあれば、それを丁寧に言語化してもらいます。 - 次への改善提案
同じ状況が起きたときにどう行動するか、あるいは他にどんな選択肢があったかを考える時間にします。
講評は、ただ褒めたり注意したりする場ではなく、気づきを共有し、次の行動につなげる“学びの場”なのです。

刺さる講評は「問いかけ」が違う【行動を変える10の一言】
人の判断や行動は、無意識のクセに左右されがちです。講評では、そうしたクセに“気づかせる”問いかけが効果を発揮します。
以下は、実際の講評で使える問いかけの例です。読者である皆さんが講評を行う時に、参考にしてもらえると嬉しいです。
- 「あなたの行動は、誰かに影響を与えていたかもしれません」(ピア効果/返報性)
- 「もし一人だったら、同じ判断をしたでしょうか?」(社会的証明/ハーディング効果)
- 「昨日だったらどうしたと思いますか?」(回想バイアス/現在バイアス)
- 「そこにいた理由、あとから考えても納得できそうですか?」(認知的不協和)
- 「なぜ最初にそう判断したのか、思い出せますか?」(アンカリング)
- 「そのやり方、あなた自身が決めた方法でしたか?」(DIY効果/保有効果)
- 「もし誰かが『すごい』って言ってたら、どう感じたと思いますか?」(好意/バンドワゴン効果)
- 「みんなが見ているとき、行動はどう変わりますか?」(シミュラクラ現象/傍観者問題)
- 「選択肢が多かったら、同じ行動を選びましたか?」(選択のパラドックス)
- 「最初と最後、どちらの印象が強く残っていますか?」(ピークエンドの法則)
これらの問いかけは、あくまで“答えを引き出す”ことが目的です。
正解を求めるのではなく、参加者が自分の中にある気づきを整理し、次の行動をより良いものにするきっかけとして使ってみてください。
訓練は“やること”ではなく、“変わること”
防災訓練を「やって終わり」にしないためには、次の3つを意識してみてください。
- 参加者が“自分で考える”シナリオを組み込むこと
- 講評で問いかけを活用し、気づきを引き出すこと
- 判断を見える化できるツールを活用すること
訓練は、誰かの未来を守るための時間です。
今日の訓練が、明日の命を守るきっかけになるかもしれません。

判断のクセを補助するツール「N-HOPS」
講評で問いかけをすることは重要ですが、それだけでは限界もあります。とっさの判断や記憶は、時間が経つと曖昧になってしまうからです。
そこでおすすめしたいのが、避難所運営支援アプリ「N-HOPS」の活用です。
N-HOPSには、判断や行動の履歴を記録し、チームで共有・振り返りができる機能があります。
- 「あの時もっと良い判断があったか」をあとから確認できる
- チーム内で判断基準を共有できる
- 講評をより具体的・実践的に深めることができる
N-HOPSは訓練現場だけでなく、実際の避難所運営にも活用できるツールです。
属人的な判断だけに頼らず、組織としての“判断の質”を高めたい方にとって、大きな助けになるはずです。