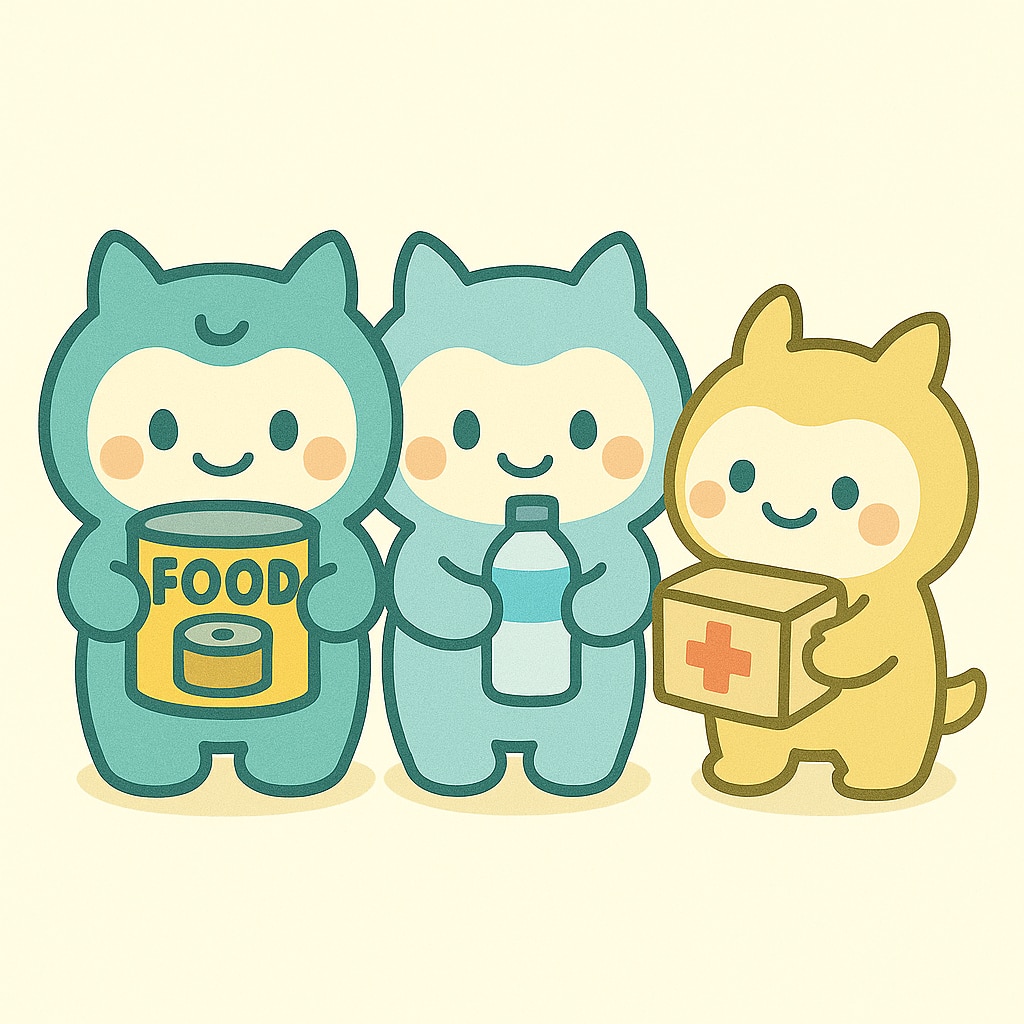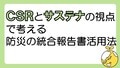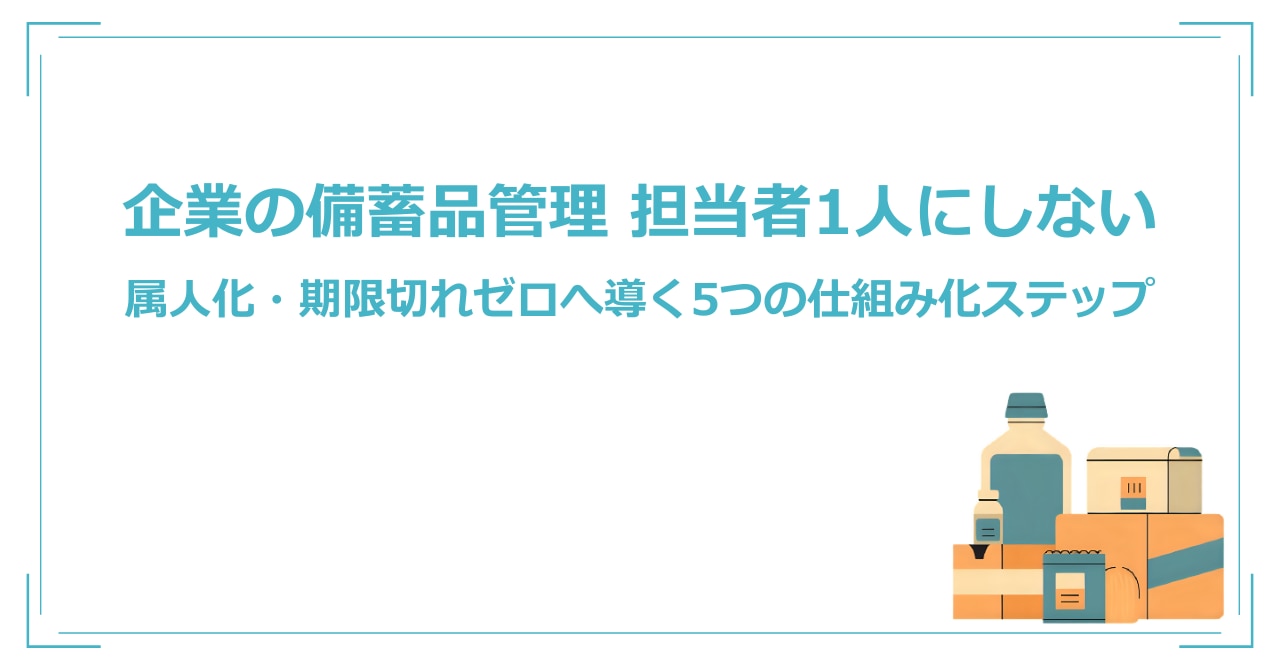
企業の備蓄品管理 担当者1人にしない:属人化・期限切れゼロへ導く5つの仕組み化ステップ
「期限切れの備蓄食が山のように出てきた」「棚卸しとその結果をExcelに入力するたび、ため息が出る」「結局、廃棄コストがかさむだけだった」──そんな経験はありませんか?
災害備蓄の管理は、担当者がひとりで抱え込むにはあまりに複雑で、手間も多い業務です。棚卸し、在庫照合、稟議・発注、社内配布、寄付、廃棄……。なかでも更新期には、これらの業務が一度に集中し、業務量が急増する時期が訪れます。
本稿では、「期限切れゼロ」「棚卸差異ゼロ」を実現するために、備蓄管理をいかに仕組み化できるかを、現場目線で解説します。ポイントは4つ。
① 棚卸しの定期化と台帳の最新版一本化
② 稟議・発注から証憑管理までの手順の定型化
③ 期限切れを防ぐリマインドと、分散管理
④ 更新と処理(寄付・廃棄・社内配布)を一体で回す運用設計
後半では、チェックリストや証憑の確認、寄付の流れまでを含む「現場で実装できるプロセス」を、全体像→手順→具体例の順にご紹介します。
Excel管理でも可能な仕組みで、毎回のため息を今日から減らしましょう。

目次[非表示]
備蓄品管理の属人化の問題点と限界
「棚卸しのたびにExcelを開いて、どの箱が期限切れかを探す」
「倉庫の奥で眠る、誰も知らない備蓄品」
「倉庫内の片隅を占有する、期限切れ備蓄品のヤマ」
――こうした「備蓄品管理あるある」は少なくありません。
多くの企業では、総務・管理部の担当者1人が兼務で備蓄品管理を行っています。更新時期になると、倉庫確認・在庫照合・稟議と発注・拠点配布、入替に伴う処理(寄付・廃棄・社内配布)まで、多くの工程を担当者が担います。日常業務の合間では後回しになりやすく、期限切れや数量不足の発見が遅れるリスクがあります。これは単なる作業効率の問題にとどまらず、災害時の初動にも影響を与えます。
備蓄品の管理はBCP(事業継続計画)の重要な要素の一つです。しかし実務では、BCP担当と備蓄担当が分かれており、情報連携が不足しやすいのが実情です。近年のガイドラインや支援資料でも、備蓄量の確保だけでなく、維持・更新体制の明確化が重視されています。属人化を解消し、誰でも運用できる仕組みを整えることで、結果的にBCP全体の信頼性が向上します。
備蓄品更新の手順
複数拠点での備蓄品の更新から処理(寄付・廃棄・社内配布)までの手順は、おおよそ次のとおりです。
- 現状把握:台帳と現物を照合(対象拠点・数量・期限)します。
- 方針決定 :入替対象を確定。処理方法(寄付/廃棄/社内配布)に沿って仕分けします。
- 計画策定 :各拠点の配布プラン(品目・数量・納期)を策定します。
- 見積取得 :(手数料・配送費)を含め見積を取得します。必要に応じて複数社比較します。
- 稟議・発注:稟議申請完了後、発注します。
- 新規受入 :検収→配置。各拠点への連絡します。
- 旧品回収 :各拠点から集約し、箱単位の明細を作成します。
- 旧品処理 :
【寄付】受入団体選定→確定→集荷・配送手配(受入条件を事前確認)
【廃棄】廃棄品目確定→日程調整→産廃処理業者へ引渡し
【社内配布】配布方法詳細確定→配布場所確保→アナウンス - リスト更新:備蓄品リストを更新します。
標準的な更新サイクルは5〜7年が多数派です。

備蓄品管理で起こりやすい課題とは?
現場では次のような課題が発生しがちです。
期限管理がExcel・紙台帳・個人メモに分散し、最新版が不明。
倉庫やフロアに点在して所在不明の箱が発生。
更新のたびに拠点配布・処理手配が重なり、担当者が疲弊。
担当交代時に履歴が共有されず、過去の発注・処理方法の経緯が追えない。
たとえExcel台帳で管理できているように見えても、複数人で同一ファイルを上書きしてしまう、社内サーバのフォルダ構成が曖昧で最新版が特定できない――といった日常的な「ミスの温床」があります。さらに、総務・BCP担当・施設管理など部署横断の業務のため、責任の所在が曖昧になり、稟議ルートが複雑化して属人化が進みます。
なお、Excel自体は有効な管理手段です。問題はツールではなく、台帳設計と運用ルールが不明確な点にあります。誰が見ても同じ手順で追跡できる「形式」と「保管場所(共通フォルダ)」を決め、更新履歴を時系列で残すだけでも、属人化は大きく抑えられます。
更新を中心に据えた「備蓄の循環サイクル」を作る
備蓄品管理は「買って終わり」ではなく、定期的に循環させる対象です。狙いは、更新を「数年に一度の大仕事」から「定常的な軽作業とし、業務を定型化すること」を目的としています。
分散更新:実態として5〜7年サイクルが多数派です。品目ごとに期限を意図的にズラす設計により、毎年少量の更新等、年度内の作業偏りを抑える方法も有効です。
更新の可視化:Excelの条件付き書式を利用し、Excelを開くと一目で更新時期がきたことがわかるようにします。
履歴の一元管理:保管場所(共通フォルダ)に入庫日・期限・数量・配布先・寄付先・証憑を時系列で保存し、誰でも追える状態を維持します。
業務の定型化:旧品処分時の判断基準、業者選定方法、社内稟議手続きの流れを文書化して整理します。
期限の定期的確認:社内グループウェアのカレンダーを利用し、数か月先や数年先の予定をリマインドとして登録します。
備蓄更新チェックリスト(簡易版)
□ 社員数×3日分で数量算定
□ 期限前(例:6か月前)のリマインド設定(Excelの場合、条件付き書式の設定で開いた時に期限がわかる)
□ 拠点別の配布/配送方法を明確化
□ 台帳=単一最新版を運用(保管場所固定・編集権限管理)
□ 棚卸(半期/年次)で台帳と現物を突合(差異ゼロ化)
□ 証憑の即時格納(受領書・寄付/廃棄証明を同フォルダに一元管理)
現場で最も重要なのは、期限切れを出さないことと、台帳と実数のズレを発生させないことです。まず棚卸の定期化と期限前リマインドの確実化で未更新を防ぎます。次に、必要に応じて期限の分散更新(ズレ管理)を取り入れると、棚卸・稟議・支出のピークが緩和され、更新が滞りにくくなります。
さらに、更新と寄付(または社内配布・廃棄)の一体設計に切り替えることで、工程の円滑化が期待できます。会社の事情により異なりますが、まずは「期限切れゼロ」×「差異ゼロ」を優先し、そのうえで分散更新と外部委託を上手く活用することが、担当者負担の持続的な低減につながります。

更新時の「配布・寄付・寄付後の確認」をまとめて効率化する
更新に伴う期限切れが近い備蓄品の処理は、実務負担の大きな作業です。廃棄にはコストと適切な委託が必要で、環境配慮の観点からも慎重さが求められます。また、寄付の場合は、寄付先選定・配送・寄付後の確認など、別の段取りが増えます。
そこで、寄付・配送・寄付後の確認を一貫して代行する仕組みを更新フローに組み込むと効果的です。更新と寄付が一本化され、担当者が最後に抱えがちな「段取りの負担」を解消できます。サステナビリティ・CSR・SDGsの観点でも実効性を高める効果があります。
「ストクル+」の寄付ネットワークは50団体以上に拡大しており、最近の事例ではアルファ米・保存水・ライスクッキー・缶入りパンを中心に、寄付先の団体は20団体を超えてます。寄付品目も、マスク・カイロといった食品以外も順次拡大し、支援現場からは、冬場に向けて「本当に助かる」という声も上がっています。また、サービス導入会社の社内では、寄付の取り組みが社内報で紹介されるなど、社内外での評価にもつながっています。
ミニ事例
入替と寄付を一本化した結果、担当者の段取り負担が減り、更新作業が一度で完了。「入替と寄付まで一度で済んで助かった。捨てずに任せられるので安心。次もよろしくね」というお声をいただいています。さらに、経営層の「寄付で社会貢献を示したい」という意向にも合致し、工数削減と証憑(寄付証明書)の可視化により、社内合意や稟議が通りやすくなりました。その結果、次回以降の計画づくりも立てやすくなりました。現場と経営の両方にメリットがある、効率と社会貢献を両立できる進め方として根づきつつあります。
寄付運用の小さなコツ
数量の箱単位明確化:品目・数量・賞味期限を一覧に整理すると寄付先の受入可否がしやすく、以降のやり取りも円滑になります。
受入団体情報整備: 団体の受入条件(期限・受取可能曜日・搬入場所・窓口)、喜ばれた品、寄付NG品目等を記録しておきます。それにより、次回の調整が速くなり、継続的な関係づくりに直結します。
拠点別寄付日の統一: 各拠点の寄付日を同一日に揃え、連絡・集荷を一括化します。さらに新規納品を同日に合わせると、入替と回収が一度の作業で完了でき、担当者の負担を軽減できます。

まとめ: 仕組みで属人化を防ぎ、持続可能な備蓄管理へ
備蓄管理の本質は、ツールではなく仕組みの設計にあります。Excelでも紙でも、「誰が見てもわかる台帳」×「分散された更新サイクル」×「寄付・寄付後の確認まで一気通貫」が整えば、担当者が変わっても運用は続きます。
この仕組み化は、担当者の効率化だけでなく、ガバナンス・監査対応・ESG経営の一環でもあります。定期的な更新と寄付の循環を継続することで、「防災」「環境」「社会貢献」を一体化した持続可能なモデルが定着します。
まずは、現状フローの可視化を起点に、台帳整備・定期棚卸の固定・手順の定型化(判断基準/稟議〜発注/証憑管理)を進めてみるのはいかがでしょうか。次のステップとして、更新と寄付の一体運用に移行し、納品と回収・証憑確認を同日に揃える設計にすると、従来工程の大幅削減と社内外の評価向上が両立しやすくなります。
サービス詳細・お問合せは以下から