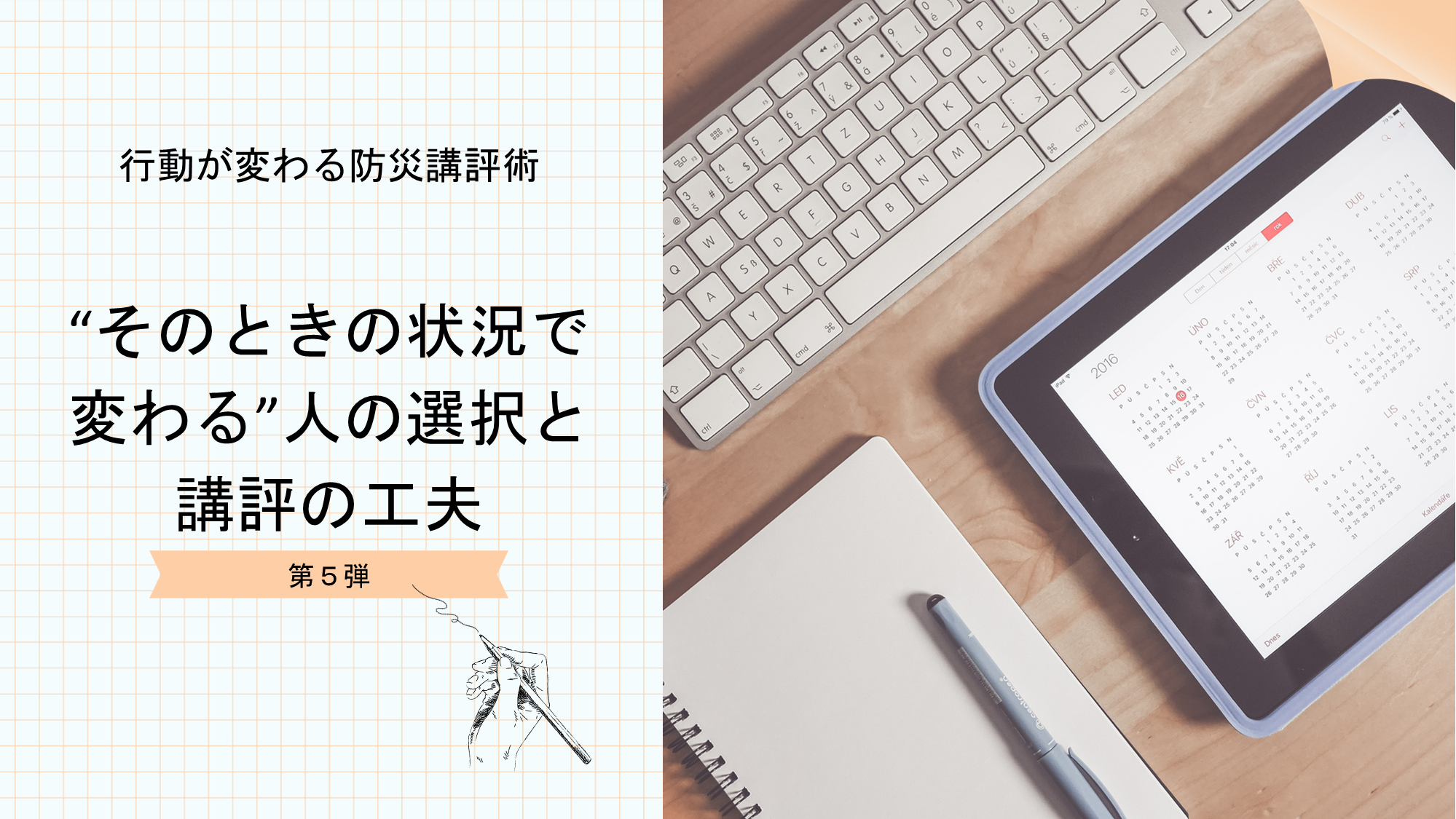
行動が変わる防災講評術⑤ “そのときの状況で変わる”人の選択と講評の工夫
「どうして動かなかったの?」と尋ねたら、 「間違ってたら怒られるかもと思って…」という返答。
同じ人が、別の場面では即座に動いていたのを見て、 私は「人の判断は“条件”に左右される」と実感しました。
避難所運営訓練では、経験や知識だけではなく、 その場の空気、制約、タイミングといった“状況条件”が、行動に大きな影響を及ぼします。
今回は、そうした「条件で行動が変わる」人間の心理に着目し、 避難所運営の講評で活かせる4つのバイアスを紹介します。

状況にとらわれる人間らしさを前提にする
避難所運営での行動のズレは、判断力や責任感の欠如だけが原因ではありません。
そのときの心理状態、周囲の目、制度的な制約など“外的な条件”に大きく影響されることがあります。
講評では、「その選択をした背景にはどんな条件があったのか?」という視点を持つことが大切です。
ここでは、避難所運営の場面でありがちな4つの心理バイアスを紹介し、 その特徴と講評での言葉がけの工夫を考えます。
■心理的リアクタンス(制限されると反発したくなる)
【どんな心理?】
「やってはいけない」と言われると、逆にそれをしたくなる反発心理が働きます。
【講評のヒント】
「“立ち入り禁止”の貼り紙に対して、逆に近づいてしまった参加者がいました。ルールの“理由”を丁寧に伝えることで、納得と自律を促せます」
■アンダーマイニング効果(外からの報酬が内発的なやる気を下げる)
【どんな心理?】
“やらされている”と感じると、本来自分の中にあったやる気が損なわれる傾向があります。
【講評のヒント】
「“言われたからやった”という姿勢よりも、“自分で判断して動けた”ことに注目した講評が、次回への自発性を高めます」
■プロスペクト理論(損をしたくないという気持ちが強く働く)
【どんな心理?】
人は、利益を得るよりも“損を避けたい”という気持ちのほうが強く働く傾向があります。
【講評のヒント】
「“動いて失敗したらどうしよう”という気持ちが、初動の遅れにつながっていました。“何もしないリスク”にも目を向けることが重要です」
■ギャンブラーの誤謬(次こそは大丈夫という思い込み)
【どんな心理?】
“前回失敗したから次はうまくいくはず”という、確率とは無関係な思い込み。
【講評のヒント】
「“前も避難しなくて大丈夫だったから今回も”という油断がありました。過去の偶然が未来を保証するわけではないと気づくことが重要です」
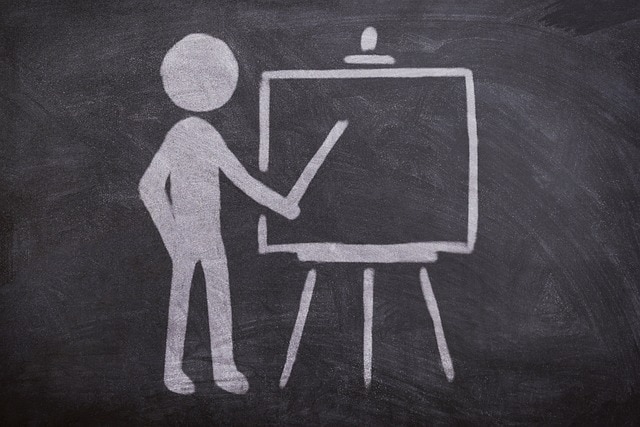
正解さよりも“どうしてその選択をしたのか”を掘り下げる
講評の役割は、単に「正しい行動」と「誤った行動」を仕分けることではありません。
大切なのは、「なぜその判断をしたのか」「何がそうさせたのか」という条件や背景に光を当てること。
そうすることで、参加者自身が“次の場面でどう選択するか”を考えるきっかけになります。
判断ミスを減らすパートナー
避難所運営支援アプリ「N-HOPS」は、 誰がどこで何をしているか、どの備品がどこにあるかといった情報を、現場で即時に共有できます。
迷いや誤解による判断ミスを減らし、落ち着いた選択ができる環境づくりに貢献します。
「状況が複雑なときほど、頼れる情報が必要です」 そんな思いで、現場に寄り添うツールです。





