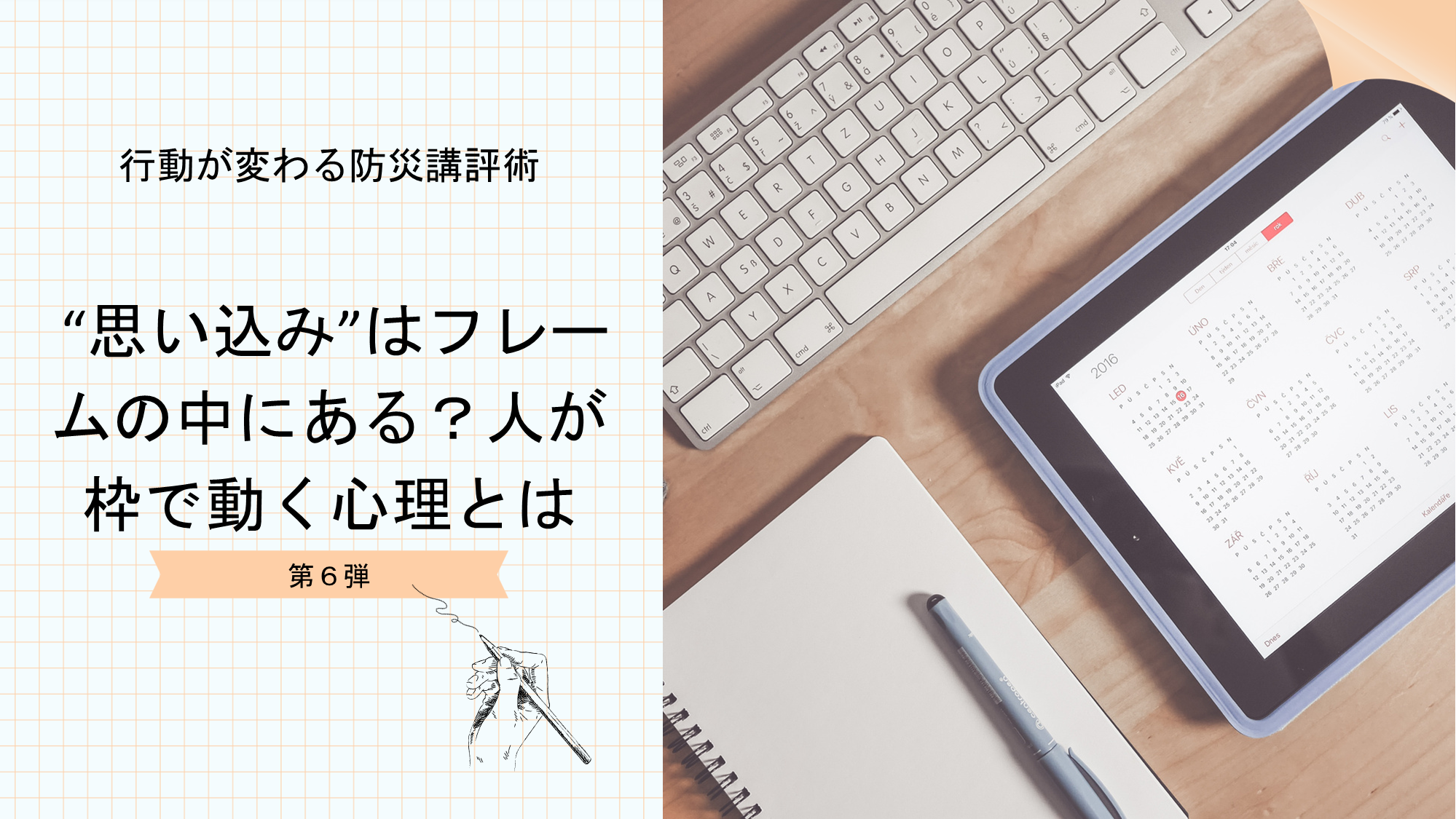
行動が変わる防災講評術⑥ “思い込み”はフレームの中にある?人が枠で動く心理とは
避難所運営訓練で「この掲示、見づらいよね」と言われたとき、私は正直驚きました。 見慣れていたせいか、自分にはとても分かりやすく感じていたからです。
そのとき改めて気づかされたのは、私の“見やすさ”は、私の“慣れ”が支えていることもあるということでした。
人は誰しも、自分なりの枠組み(フレーム)で物事を理解しています。 そのフレームは、育ってきた環境、立場、経験によって全く異なるものです。 だからこそ、避難所での情報伝達や協働には、“思い込み”や“決めつけ”が壁になることもあるのではないでしょうか。
今回は、「人は枠組みで理解する」というテーマから、避難所講評で活かせる5つの心理バイアスを紹介していきます。

情報も人も、枠で見てしまう
人は全てを客観的に理解できるわけではありません。 限られた情報や先入観、過去の経験から判断をしています。
そういった判断で用いられてしまうのが「枠組み(フレーム)」といったものです。
このフレームは設計や表現、順番の工夫によって補正もできれば、強化もされてしまいます。 講評では、「どんなフレームで見ていたか」に気づかせることが、行動変化の一歩になります。
■アンカリングとプライミング(最初の印象が基準になる)
【どんな心理?】 最初に提示された情報や印象が、その後の判断や行動に大きく影響する。
【講評のヒント】 「掲示や説明が“どう始まるか”で、理解のハードルが変わります。最初の印象づくりが、全体の伝わり方を左右します」
■キリのいい数字効果(ざっくりした数字に安心する)
【どんな心理?】 人は“5分”“10個”など、区切りの良い数字に安心感を持ちやすい。
【講評のヒント】 「“10分でできる”など区切りの良い表現が、参加者の心理的な負担を下げていました。数字の“丸さ”が行動に影響するんですね」
■プラセボ効果(気の持ちようで成果が変わる)
【どんな心理?】 効果がなくても“効く”と信じることで、実際に行動や感覚が変わる。
【講評のヒント】 「“このカードを持っていれば大丈夫”という言葉で、安心して動ける参加者が多くいました。気の持ちようも、大切な要因です」
■選択のパラドックス(選択肢が多いと選べない)
【どんな心理?】 選択肢が多すぎると迷いやストレスが増え、かえって決断しにくくなる。
【講評のヒント】 「3種類の避難ルートを提示したとき、かえって動きが止まった様子がありました。選択肢は“ある程度絞る”ことが重要です」
■フレーミング効果(伝え方で印象が変わる)
【どんな心理?】 同じ内容でも、言い回しや表現で受け止め方が大きく変わる。
【講評のヒント】 「“混雑するから別ルートへ”と“スムーズに動けます”では、後者の方がスッと受け入れられていました。表現の選び方が、納得感を変えます」

違うフレームで見ていたかもしれない
講評では、訓練の運営側と参加者側の視点に着目してみると良いでしょう。「運営者が見ていた枠組み」と「参加者が見ていた枠組み」が違っていた可能性に目を向けることが大切です。
情報の出し方、指示の順番、伝える言葉。 それらが、相手の枠組みにどんな影響を与えていたのかを振り返ってみましょう。
それが、次の訓練での“伝え方の改善”につながります。
フレームの違いを埋めるツール、N-HOPS
避難所運営支援アプリ「N-HOPS」は、 役割・情報・動線を視覚的にわかりやすく“見える化”することで、 それぞれが持つ“枠組みの違い”による認識のズレを減らします。
「伝えたつもり」ではなく「伝わる」情報設計。 それが現場の混乱を防ぐ鍵になります。





