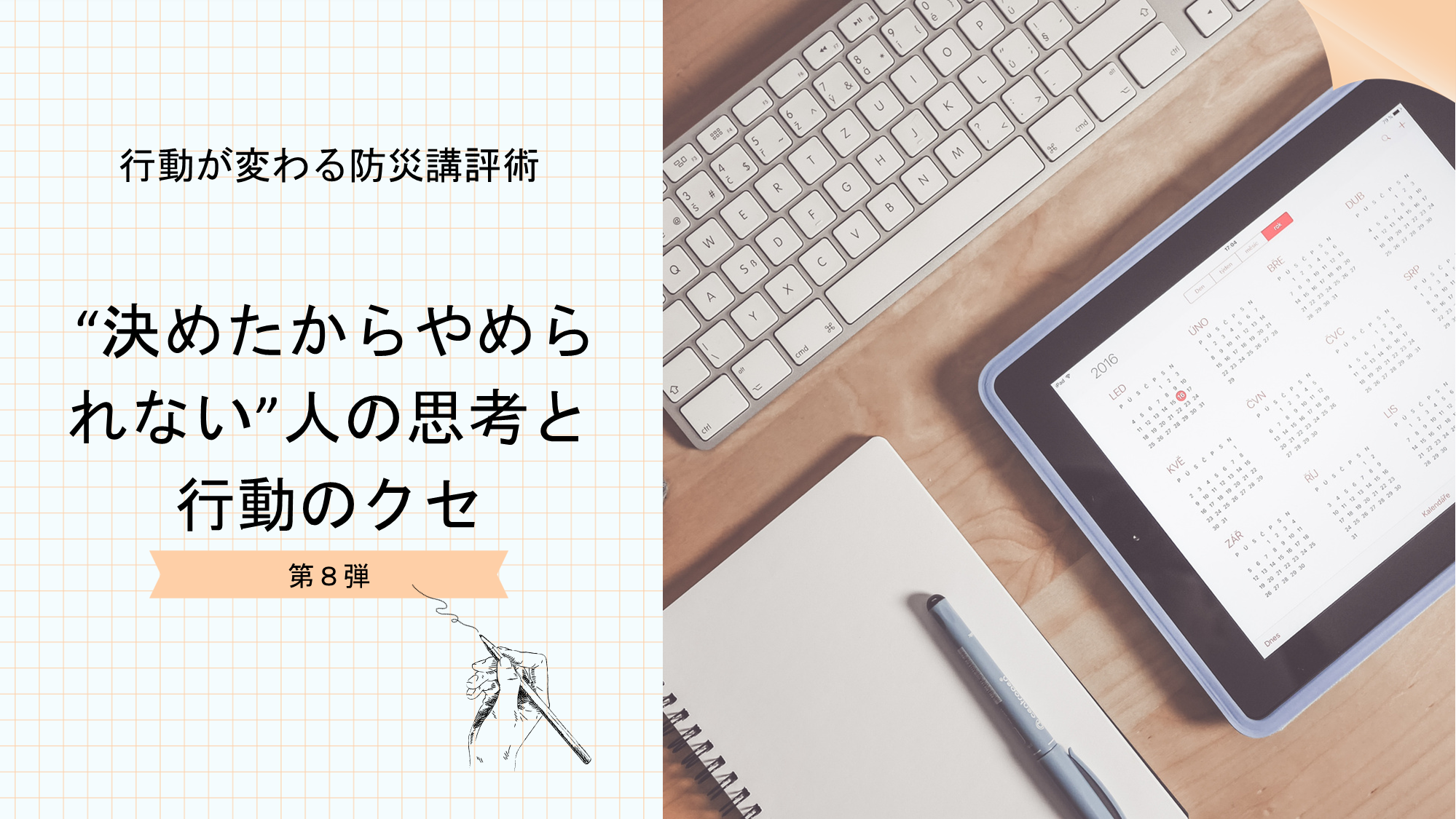
行動が変わる防災講評術⑧ “決めたからやめられない”人の思考と行動のクセ
避難所訓練で、ある高齢の参加者が「一度決めた場所から動かない」と言い張る場面がありました。こんなシーンは意外とあるあるではないでしょうか?
その場所は実際には危険で、移動した方が安全なのは明らか。 でもその方は、「最初にここって言われたから」「今さら動くのも面倒だし」と言って動こうとしませんでした。
「ちょっと頑固な人だなあ」と見てしまいがちですが、実はこれ、放っておくと避難所全体の行く先を左右するような事態につながることもあります。
なぜ人は、一度した決断にこんなにも縛られてしまうのでしょうか。 そこには“思考のクセ”としてのバイアスが影響しています。 今回は「決断が行動を縛る心理」に注目し、講評に活かせる3つのバイアスを紹介します。
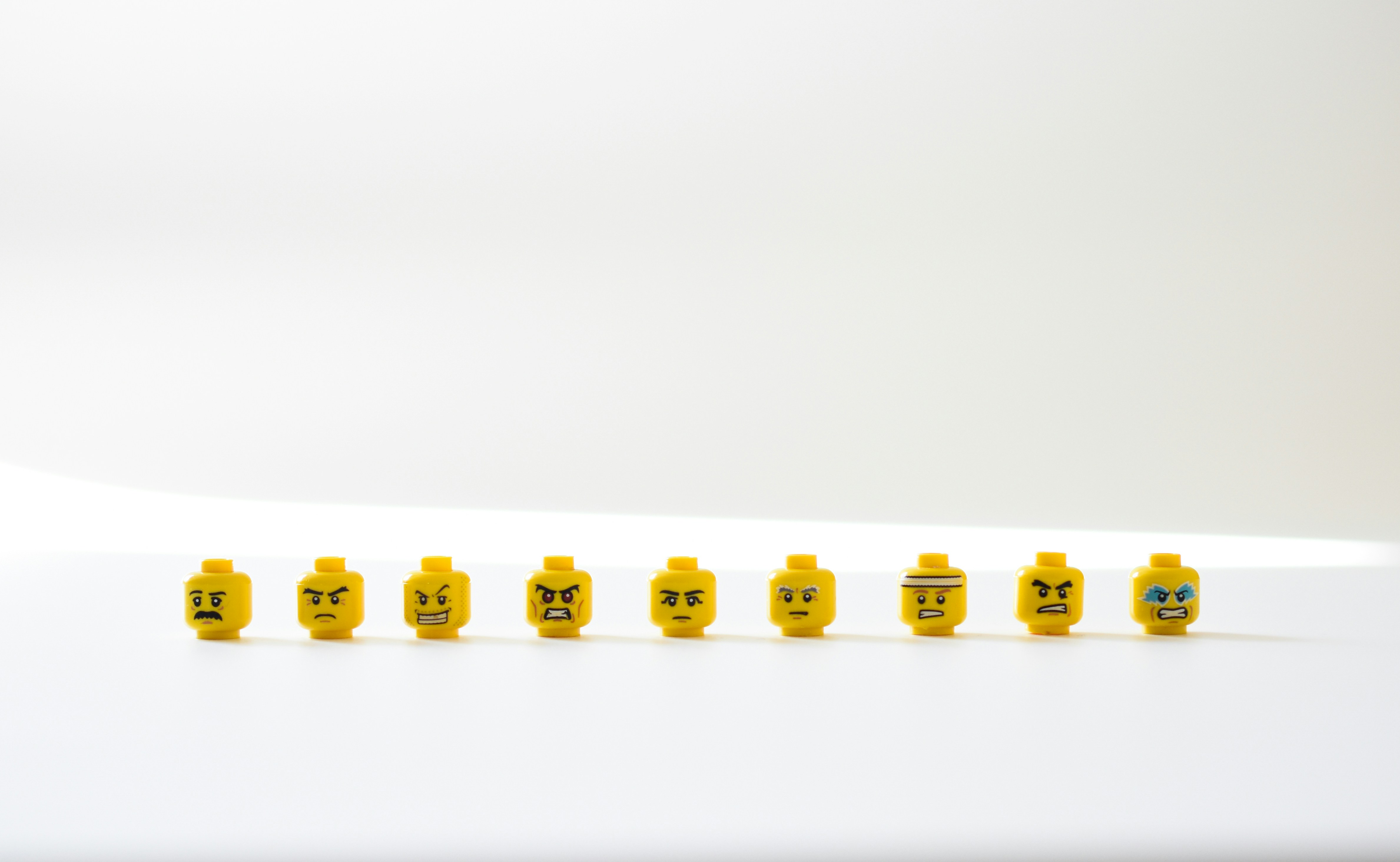
決断は、行動の“標識”になる
人は、一度決めたことを変えるのが苦手です。
とくに経験を重ねてきた世代ほど、“これまでのやり方”に安心感を抱き、変化をためらう傾向があるように感じます。長年の経験や習慣がある分、変化を受け入れにくい場面も見られるかもしれません。
理由はさまざまですが、多くの場合「自分の判断が間違っていたと思いたくない」気持ちや、「一度言ったことを覆すのは恥ずかしい」といった心理が影響しています。
その結果、訓練中でも「一度こうすると決めたから」と非合理な行動を続けてしまうことがあります。
講評では、その“決断の影響”を丁寧に読み解くことが、参加者の気づきにつながります。
■サンクコスト(もったいないの罠)
【どんな心理?】 今までの努力や時間、労力をムダにしたくないという気持ちが、誤った選択を続ける原因になる。
【講評のヒント】 「その場で見直す勇気が結果的に被害を減らします。“続けること”だけが正解ではありません」
■認知的不協和(セルフ洗脳)
【どんな心理?】 「自分の選択は正しかった」と思いたいがために、後から理由をこじつけてしまう。
【講評のヒント】 「“あの判断は正しかった”と振り返りたくなる気持ち、誰しもあります。客観的な振り返りが大切です」
■一貫性(固執と結び付け)
【どんな心理?】 一度表明した意見や行動を変えるのは、信頼を損なうように感じ、柔軟性を失いやすい。
【講評のヒント】 「“自分のやり方にこだわった”場面がありました。環境や状況の変化を味方につけましょう」
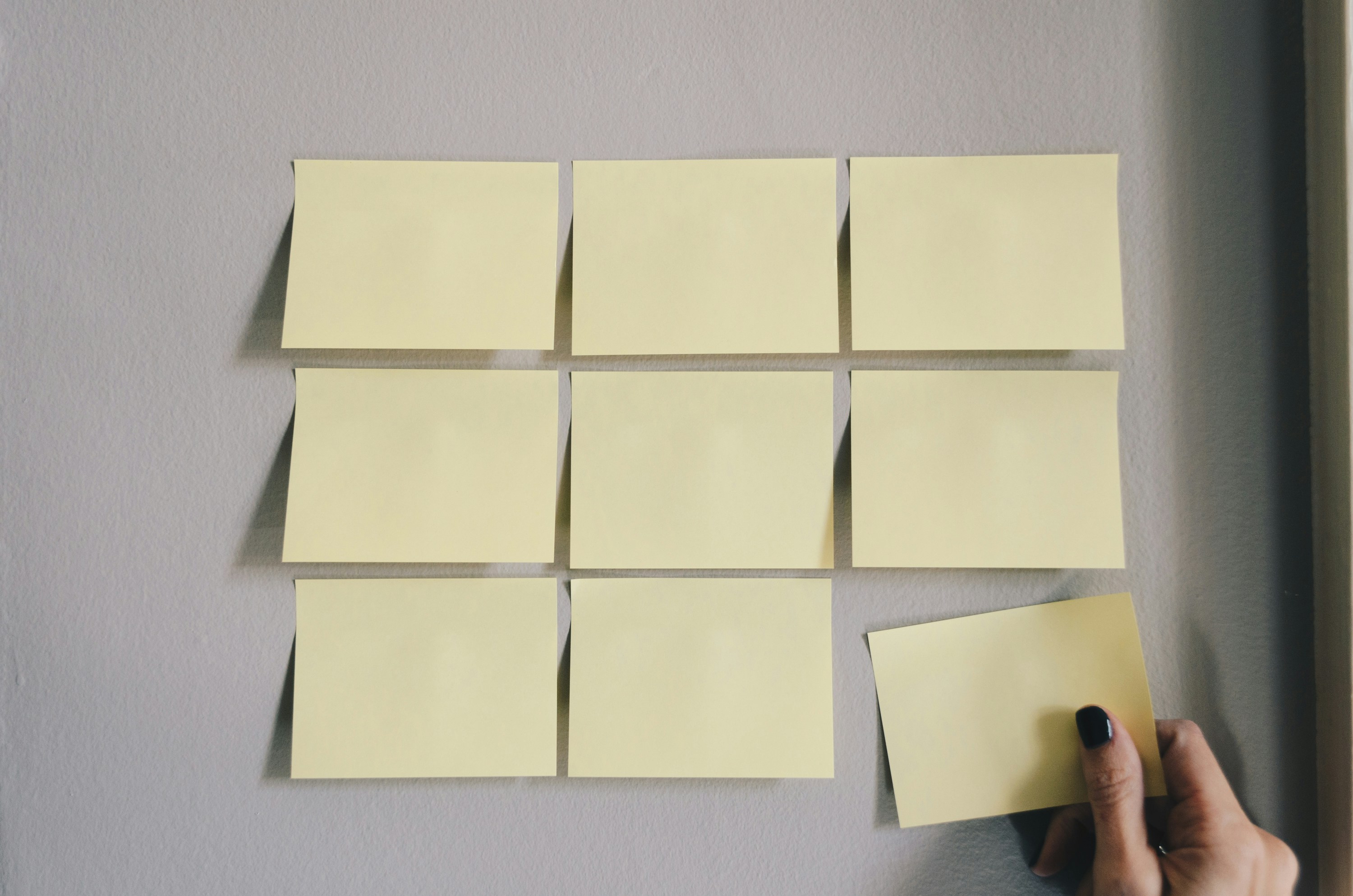
避難所運営では、軌道修正の判断力が命を救う
避難所という現場は、予測不能なことが次々と起こります。 その中で、「最初に決めたから」「これまでそうだったから」という理由で動きを止めてしまうのは大きなリスクです。
講評では、あらためて「決断した内容は、今も最善か?」を問い直すことが、参加者の思考に柔軟さを取り戻す第一歩になります。
判断の柔軟性を支えるツール、N-HOPS
避難所運営支援アプリ「N-HOPS」は、 そのときどきの判断を“見える化”し、後からでも柔軟に見直せる設計が特長です。
判断ミスを責めるのではなく、軌道修正の判断をサポートする。 N-HOPSは、そんな“進化する現場”を支えるツールです。
ここまでお読みいただき、ありがとうございました
全8回にわたってお届けしてきた「行動が変わる防災講評術」シリーズ、いかがでしたか?
それぞれの心理バイアスを切り口に、講評に活かせる視点を紹介してきました。
防災講評は、単なる振り返りではなく、参加者の「次の行動」を引き出すための大切な場面です。 このシリーズが、みなさんの講評に少しでも役立つ視点になれば嬉しく思います。
引き続き、現場での気づきや学びを大切にしながら、より良い避難所運営の実現を一緒に目指していきましょう。





