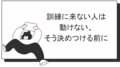避難所へのタブレット導入が増えている理由ーその先にある共助の再定義へ
ここ数年、避難所へのタブレット導入が全国の自治体で進んでいます。
規模や地域を問わず、タブレットを使った避難所運営の改善に取り組む事例が次々と登場しています。
背景には、避難者の受付の効率化や、物資要請・報告業務の迅速化といった、現場の職員にかかる負担を軽減したいというニーズがあります。
特に人員が限られる災害初動では、紙による手書き名簿や電話・FAX連絡では限界があります。
タブレットは、こうした実務の即応性を高める道具として、現場からの信頼を集めつつあります。

タブレット化が変える「避難所マニュアル」の在り方
こうしたタブレットの導入が進む中で、「マニュアルもデジタル化すればいいのではないか?」という声もあります。
確かに、避難所運営マニュアルをタブレットに格納しておけば、分厚い紙ファイルを持参せずに済みますし、資料が行方不明になるリスクも減ります。
実際、すでにPDF化したマニュアルをタブレットに搭載して配備している自治体もあるかもしれません。整理性の面では、大きな一歩です。
しかし――情報が整理されていても、「今、自分がどう動くべきか」がすぐに見えるとは限りません。
どのページに何が書かれていたかを思い出し、読み取り、判断し、共有する。その一連のプロセスを、災害の混乱の中でスムーズにこなすのは簡単ではありません。
そして私たちは、こうした課題を「訓練を重ねて慣れていくこと」で乗り越えようとしてきました。
「熟練者前提」の避難所運営が抱える見えないリスク
現場をよく知る皆さんであれば、避難所運営の複雑さは十分ご存じでしょう。
だからこそ、「訓練」「経験」「判断力」が必要だとされてきました。
ですが、ここにひとつの問いがあります。
本当に、すべての人が熟練者でなければ、避難所はうまく回らないのでしょうか?
被災直後、職員も住民も不安や混乱の中にいます。マニュアルをすぐに開いて、自信をもって判断できる人ばかりではありません。
「共助が大事」と言いながら、“共助できる前提”があまりにも高すぎる。そんな構造になってはいないでしょうか。
実際、受付DXの実証実験を行ったある自治体では、高齢者やスマホ非所持者がQRコードの読み取りに難しさを感じ、「結局紙の方が安心だ」と言って戻ってしまう例も報告されています。
「誰でも、すぐに、共助に参加できる」ための仕組みが必要だ
ではどうすれば、誰もが避難所で「動ける側」になれるのでしょうか。
そのヒントが、能美防災が開発した避難所支援ツール「N-HOPS」です。
N-HOPSは、マニュアルの代替ではありません。
マニュアルに書かれた内容を、役割や状況に応じて“今この瞬間に必要な行動”として提示する仕組みです。
タブレットやスマートフォンで誰でも直感的に使える
現場での行動を「項目」として明確化
他の人の動きも可視化され、連携しやすい
経験や習熟度に関わらず、行動に参加できる
つまり、N-HOPSは「共助を自動化するツール」として機能します。
「がんばる」から「仕組みでできる」へ。これは、避難所運営の前提を変える提案です。
守りたい人がいる。だからこそ、備えるのは“人”ではなく“仕組み”。
避難所運営の本質は、「どうすれば目の前の命を守れるか」に尽きます。
そのとき、タブレットは単なる機器ではなく、「共に動ける」関係性をつくるツールになります。
N-HOPSは、避難所の共助を“実装”するしくみです。
もし、あなたが「守りたい人」がいるなら。
もし、現場で迷う誰かを支えたいなら。
次に備えるのは、マニュアルの整備や訓練だけではなく、“共助が立ち上がる設計”かもしれません。