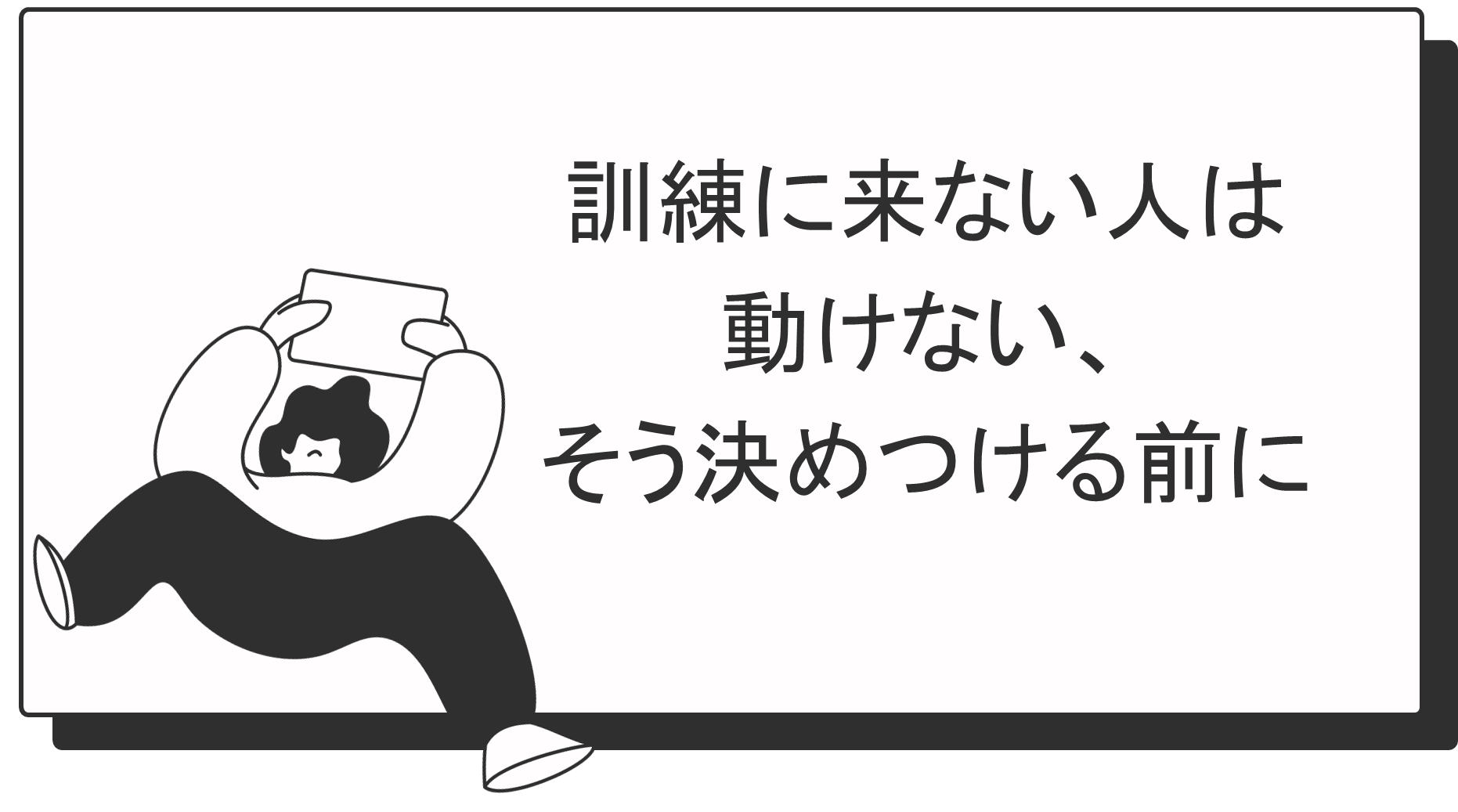
「訓練に来ない人は、動けない」──そう決めつける前に
先日、地域の避難訓練に参加させていただきました。
平日の夜にもかかわらず、多くのスタッフが集まり、手際よく会場を設営し、役割分担をこなしていました。自主防災組織のメンバーと話す機会があり、こんな言葉が印象に残りました。
「新しい人を訓練に参加してもらうのはかなり難しいんです。声をかけてもなかなか来てもらえないし…訓練に来てもらえないと、いざという時に動けないんですけどね」
その言葉には、責めるでも諦めるでもなく、ただ地域の現実を丁寧に見つめてきた人の重みがありました。
地域を何とかしたい。でも、訓練の現場はいつも同じ顔ぶれ。そんな葛藤が、そこにはありました。
目次[非表示]
「訓練に来ない人は、動けない」──本当にそうでしょうか?
- 「今年も来たのはいつものメンバーだった」
- 「新しい人にも声はかけている。でもなかなか来てもらえない」
- 「結局、いざという時に頼れるのは経験のある人たちだけ」
その実感は、現場で日々向き合っている方々だからこそ強くあるのだと思います。
それでも、あえて今、こんな問いを投げかけてみたくなるのです。
本当に、訓練に来ない人は、共助の輪に加われないのでしょうか?
動ける人を増やす方法は、「訓練に来てもらう」以外に、本当にないのでしょうか?
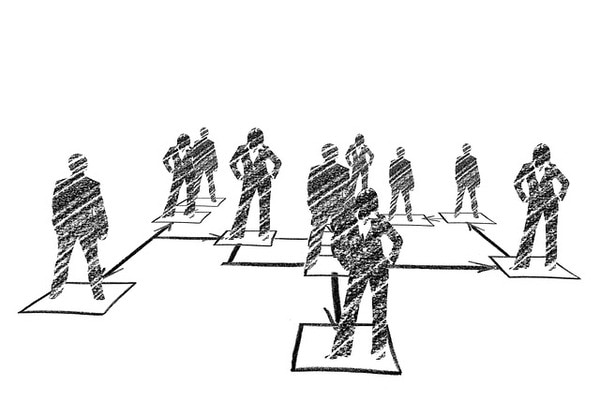
ヒアリングから見えてきた意外な本音
私たちが行った住民へのヒアリングの中で、こんな声がありました。
「正直、時間は割きたくない。でも、共助には関わっていたい」
「訓練しなくても、いざというときに動けるように見られたい」
それは身勝手ではありません。
人前で失敗したくない、自分の時間を大切にしたい、でも“地域を見捨てたくはない”。
そんな葛藤や不安が、行動の背後にあるのだと気づかされました。
共助を、「訓練済みの人たちだけ」にしないために
防災マニュアルが整備されていても、内容を本当に理解している人は限られます。
訓練に参加できる人を前提とした運営では、どうしても「一部の人」で支える構造になりがちです。
けれど、実地の訓練が難しい人にも“想像力”や“疑似体験”を通じて、備えの準備ができるとしたら――。
「来ない人」にも、共助の入り口が開けるのではないでしょうか。

N-HOPSは「あなたを熟練者にしてくれるアプリ」です
能美防災が開発中の「N-HOPS」は、避難所運営を支援するためのタブレットアプリです。
現場で求められる流れや判断を、シミュレーション形式で体験できる設計になっています。
- よくある避難所の困りごとに「あなたならどうする?」と問いかける
- 手順や役割を、視覚と選択肢で確認できる
- マニュアルを場面別に再構成し、必要なときにすぐ取り出せる
訓練の参加が難しい人でも、頭の中で“何度も予行演習”を重ねておける。
N-HOPSは、そんな新しい共助力の育て方を提案します。
来ない人も、地域の力にできる
私たちは、全員が防災のプロになることを求めているわけではありません。
でも、「参加しない人=無関心な人」と決めつけるのではなく、
その人が“動ける状態”になれるように支援することはできると信じています。
N-HOPSは、その仕組みのひとつです。
共助を、あきらめない
防災を担うみなさんが、現場で抱えている不安やもどかしさ。
それは、責任感とともに、「もっと良くしたい」という思いの裏返しだと思います。
共助を、あきらめたくない。
でも、今のままでは限界がある。
だからこそ、できることから変えていきたい。
N-HOPSは、そんなあなたの思いに応えるためのツールです。




