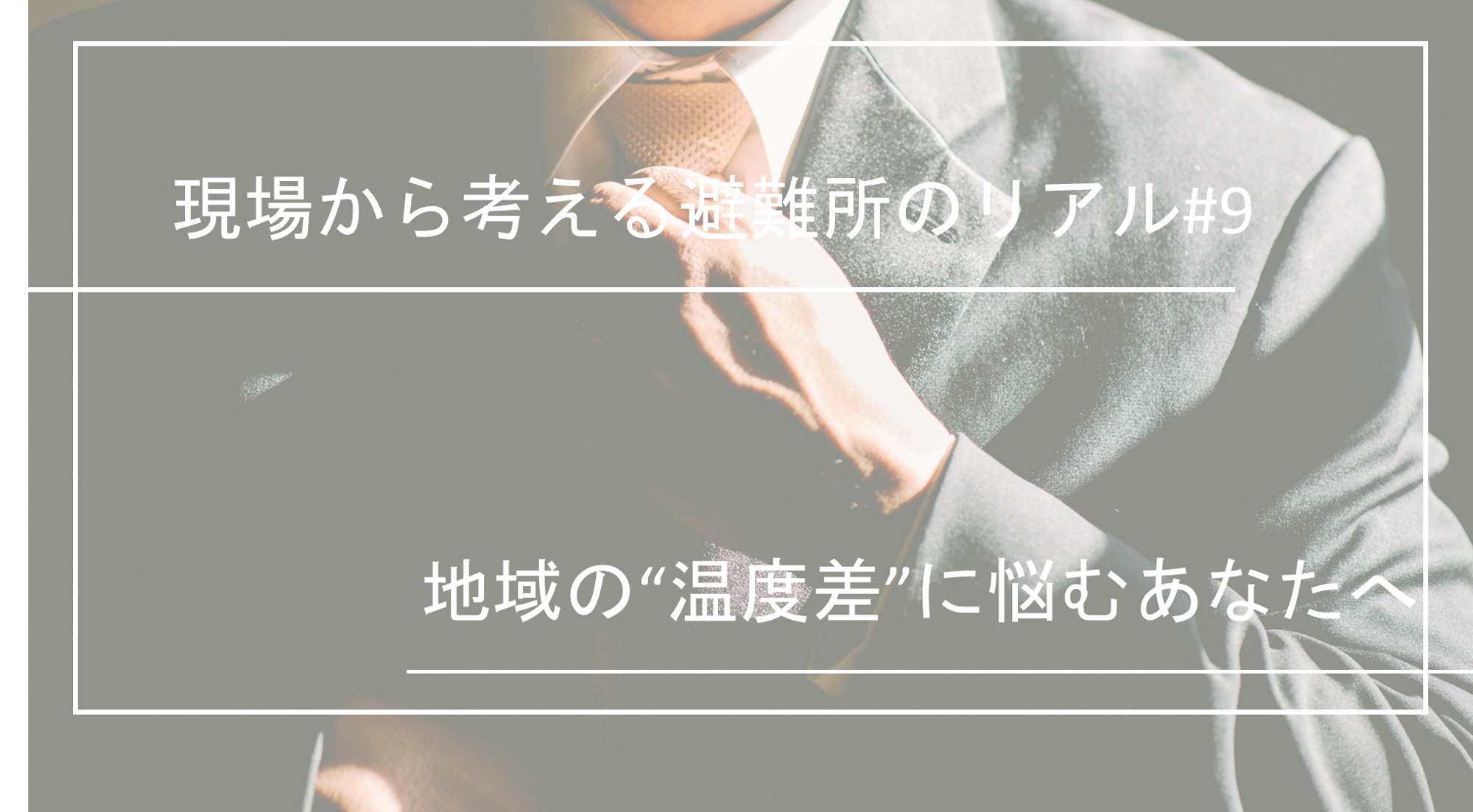
現場から考える避難所のリアル #9|地域の“温度差”に悩むあなたへ
大雨警報が出れば防災担当課が参集し、警戒レベル3で避難所が開設される。
これは多くの自治体で共通するオペレーションでしょう。
しかし、いざ避難所を開けようとしたとき、こうした声が現場から聞こえてくることがあります。
「協議会が想定通りに動けない」
「キットはあるけど、使い方がわかっていない」
「結局、職員が全部やるしかない」
どの自治体にも、防災協議会や自主防災組織は存在します。
でも、“活発に機能している”と胸を張って言える地域は、果たしてどのくらいあるでしょうか?
目次[非表示]
地域差?人の問題?――「温度差」の背景
ある自治体では、約30か所の避難所にそれぞれ協議会がありながら、「活動に温度差があるのが正直なところ」と打ち明けてくれました。
中には、協議会が年に数回訓練を企画し、防災士が中心となってキットの中身まで見直すような事例もあります。
一方で、「会長が高齢で動けず、誰がやるのか決まっていない」「訓練は5年以上やっていない」といった声も少なくありません。
特に課題が深刻なのは、避難所の開設スピード。
「区の参集職員が開設しようとしても、協議会の協力がないと受付や誘導が始められない」
「町会の体制ができていないところは、開設までに数時間の差が出ることもある」
というリアルな声が聞かれました。

なぜ温度差が生まれるのか?
防災協議会の多くは町会や自治会を母体に設置されます。
設立当初の熱量が維持されず、リーダー交代や住民の高齢化によって“形だけ”の存在になってしまうことも珍しくありません。
また、職員側にも悩みがあります。
「避難所開設キットを整備しているのに、存在すら知らない協議会がある」
「判断を住民に任せたいが、責任は最終的に職員が持つことになる」
こうした板挟みに、現場の防災担当職員は日々悩まされています。
一歩を踏み出すには:温度差を埋めるアプローチ
●「熱い拠点」をモデル化する
特定の学校区では、防災士7〜8名が中心となって独自の訓練やマニュアルの修正を実施。
こうした「熱い拠点」をモデルケースとし、他地区にノウハウを伝播することが効果的です。
●視覚で伝えるツールを使う
実際、ある自治体では、文字情報ではなく「開設の動きが図で分かるキット」を導入したことで、理解度と参加意欲が大きく向上しました。
●住民と職員の「間」を埋める中間支援
防災士や若手PTAが、町会役員に代わって実働する例も出てきています。
協議会任せにせず、“第3の担い手”を支える仕組みが重要になりつつあります。
変えられるのは、あなたの地域かもしれない
防災協議会に温度差があるのは、全国どこでも抱える悩みです。
でも、制度と現場のギャップを埋めようとする小さな工夫が、やがて地域全体の防災力を押し上げていきます。
あなたの地域にも、次の「熱い拠点」を生み出す余地がきっとあるはずです。
避難所運営を“動かす”ためのデジタルツールをお探しなら
避難所開設キットの電子化・マニュアル整備・協議会支援など、
地域と職員の“間”を橋渡しするツールをご検討中なら、
N-HOPSがサポートいたします。




