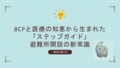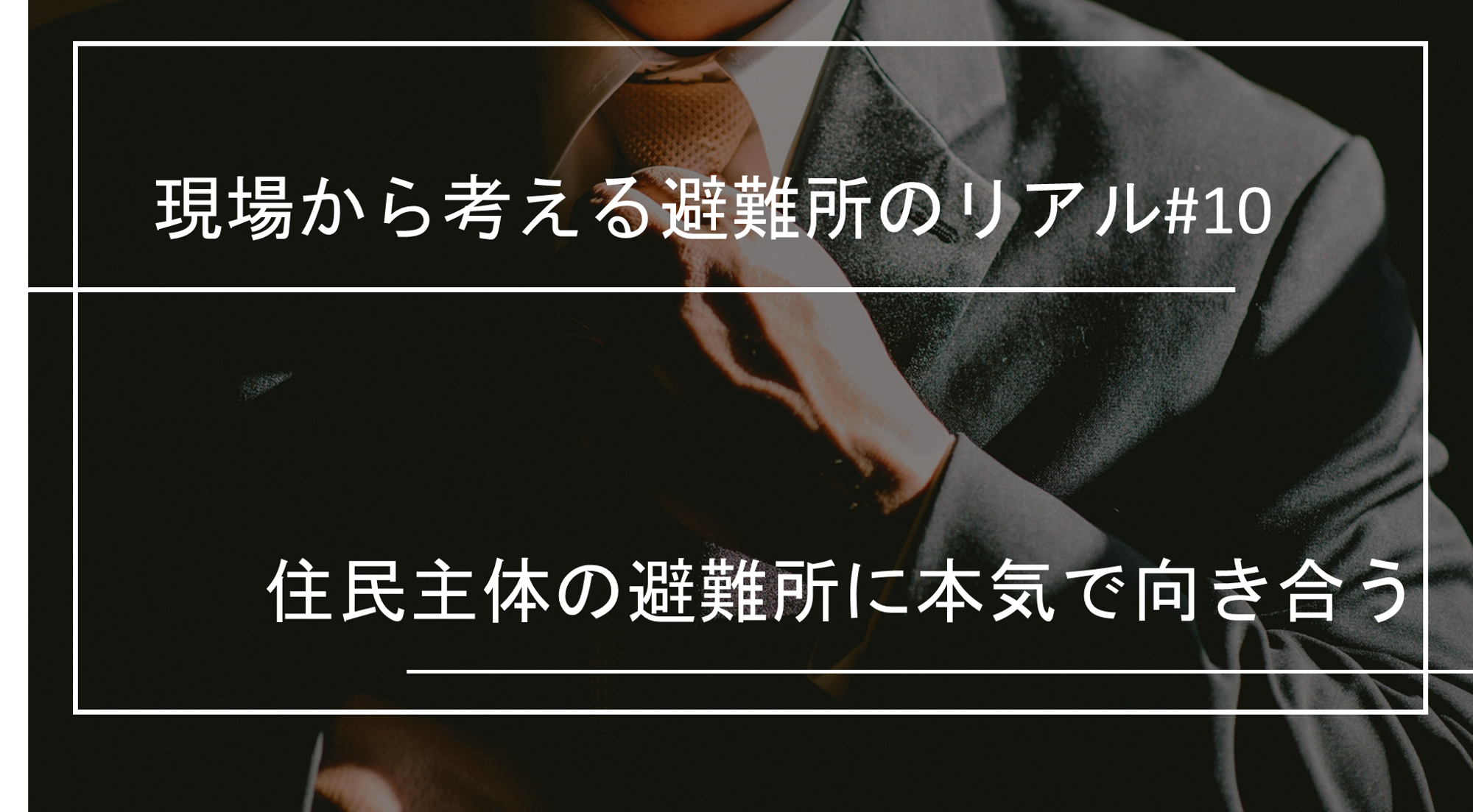
現場から考える避難所のリアル #10|住民主体の避難所に本気で向き合う
「ウチの区は、震度5弱以上の地震が起きたら、まず住民が鍵を開けて避難所を立ち上げることになってるんです」
そう語ってくれたのは、ある自治体の防災担当職員。
先日、私たちは実際にその現場を訪ね、防災担当者の“生の声”を伺いました。
開口一番に返ってきたのはこうです。
「職員が来られない前提で、もう全て組んでいます」
目次[非表示]
現場のリアル:「最初に動くのは住民です」
この自治体では、ほとんどの職員が区外在住。
災害時に庁舎に集まれないことを前提に、避難所開設の初動は地域住民が担うよう設計されています。
鍵の管理も、開設も、ゾーニングも、レイアウトも。
そのすべてが「避難所運営管理協議会」や、日頃から訓練を重ねた住民の手によって進められます。
とはいえ、彼らに「やってください」と言うだけでは足りません。
そこで導入されたのが、誰でも使えることを目指した避難所開設キットでした。
「誰でもできる」を支えるキット。しかし、現場の声にはこんな声も。
実際に見せてもらったキットはよく設計されていて、
手順やゾーニング例、避難者への声かけの方法まで網羅されていました。
ですが、その運用に関して、ある職員はこう漏らしました。
「内容を変えたいんです。でも、そのたびに業者に依頼するのは正直大変で……」
納品されたキットの内容は、完成品の「冊子+紙資材」として保管されており、
変更や更新を加えるには、外部業者に依頼するか、区の職員がデータ編集するしかないのが実情。
「いざというときに“この掲示は古かったな…”と気づいても、すぐに直せないんです」
さらに、備蓄倉庫に保管しているため、場所が分かりづらい・キットの存在を忘れてしまうといった声も。
「良くできたツールなのに、“使いたいときに使えない”もどかしさがあります」と職員は話してくれました。

「使い回し」ができないアナログと、柔軟性のあるデジタルの補完関係
アナログキットの良さは、誰でも手に取りやすく、視覚的に直感的なところにあります。
しかし一方で――
- 各避難所に合わせた個別編集がしづらい
- 情報の更新が属人的・手作業になりがち
- どこにあるか分からない、誰が持ち出すか不明瞭
- 利用履歴が見えないため“備えがどこまで共有されたか”把握できない
といった「見えない困りごと」が、現場には確かに存在していました。
住民が「動けるようにする」には、ツールの見える化・更新性が鍵
避難所は、制度ではなく“人”で動きます。
その“人”を動かすためには、ツールが「わかりやすい」だけでなく、「アップデートしやすい」こと、「どこで使われているか把握できる」ことが大切です。
防災担当職員はこうも語っていました。
「このキットを“ちゃんと使ってる”痕跡があると、職員としては安心できるんですよね。
逆に、長年しまわれっぱなしだと……不安になりますよ」
避難所運営を“今”に合わせて、柔軟に・見える形で支えるなら
N-HOPSでは、避難所開設・運営に必要な情報を、デジタルで一元管理できる仕組みを提供しています。
「誰が使ったのか」「内容は最新か」「住民が把握できているか」――
アナログの限界を補いながら、現場を支える仕組みを目指しています。